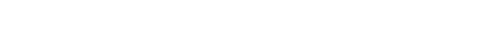物流倉庫の自動化が進む今、それでも「人の動き」の凄さを実感する瞬間
物流業界における「自動化」は、ここ数年で急速に進んできました。国内でも深刻な人手不足が続き、
特に倉庫現場では高齢化や人材確保の困難さから、自動化への投資が加速しています。
そこへ登場するのが、いわゆる最新のマテハン(マテリアルハンドリング)機器たちです。
自動倉庫、AGV(無人搬送車)、AMR(自律走行ロボット)、ピースピッキングロボット、仕分けロボット…。数年前までは「未来の話」だったこれらの機器が、今やEC大手企業が自社物流で導入したり、
3PL大手の物流会社が導入するだけでなく、中小規模の物流現場にも徐々に導入されるようになっています。
SDGs対策や国の補助金制度が充実した背景があったのも影響しているかもしれません。
最新マテハンが実現する「効率化」と「省人化」
最新のマテハンの強みは、なんといっても「正確さ」と「安定した作業スピード」です。
例えば、AGVやAMRは、センサーやマッピング技術を駆使し、人や障害物を避けながら最適ルートで
荷物を運搬します。人がフォークリフトや台車で移動するのに比べ、衝突事故のリスクも低く、
24時間稼働が可能という点も大きな魅力です。
ピースピッキングロボットも進化を遂げています。従来は同じ形状の箱や決まった商品のみしか
扱えませんでしたが、AIによる画像認識技術の向上で、サイズも形も異なる商品をつかみ、
移動させられるようになりました。EC需要の増加により、多品種少量ピッキングのニーズが高まる中で、
こうしたロボットは物流業界にとって救世主といえる存在です。
導入検討の現場で感じる「人の動き」の凄さ
しかし、最新のマテハンを検討する現場に立つと、必ず直面するのが「人の凄さを改めて痛感する瞬間」でも
あります。
ロボットは確かにすごい・・けれど、人はそれ以上にすごいのです。
例えば、棚からピッキングを行うとき。
人は、商品がどこに置いてあるかを感覚的に把握しながら、視覚・聴覚・触覚を総動員して最短ルートで
商品を取り出します。近くの別の商品を避けたり、別の指先で荷物を支えながらラベルを確認したり、
一連の動作が一秒単位で連携しています。
これはマテハン機器ではまだ再現が難しい「同時処理能力」や「状況判断力」によるものです。
AGVやピッキングロボットも、プログラムされた動きは非常に正確ですが、作業内容が変化したときや、
想定外の事態が起きたときにはすぐに止まってしまうこともあります。
また、段ボールのつぶれ具合を指で感じ取ったり、わずかに箱が滑りやすい素材であることを
瞬時に察知して持ち方を変えるなど、人の繊細な感覚は今も機械では完全に代替できません。
自動化と人の共存こそ、現場の現実解
物流業界において「自動化が進むから人が不要になる」という意見を耳にすることもありますが、
まだまだ人にしかできない事は多くあります。
実際、多くの倉庫で目指されているのは「人とロボットの協働」です。単純で繰り返しの多い作業や、
重い荷物の搬送などはロボットに任せ、人は例外処理や臨機応変な対応に集中する。
こうすることで作業負荷を減らし、人材不足の解消につなげるのが、今の現実的な自動化の方向性のようです。
マテハンを導入するにはある程度のスペース・空間が必要になり、入庫~保管~出庫まで効率的に行うには
1フロアで完結する仕組みが最適です。その為には物量にもよりますが、1,000坪単位で倉庫を用意する
必要性もあり、設置工事や準備期間でかなりの資金や時間を要します。
特に中小規模の倉庫では、投資できる額にも限りがあり、すべてを自動化するのは現実的ではありません。
だからこそ、「どの作業をロボットに任せるか」「人の強みをどこに活かすか」を見極める目が
非常に重要となります。
導入の現場では、最新のマテハンのデモンストレーションを見て感動する一方で、
「やっぱり人の動きはすごいな」と感心させられる場面が何度もあります。
それは、人の作業が決して単純ではなく、経験と感覚、そして瞬時の判断力で成り立っているからです。
物流現場の未来は、間違いなく自動化なしには語れません。
しかし、だからといって人の役割がゼロになるわけではなく、むしろ人にしかできない部分が
いっそう際立つように思います。
最新マテハン導入を検討するほどに、「人の動き」の偉大さを改めて感じております。 矢野