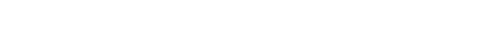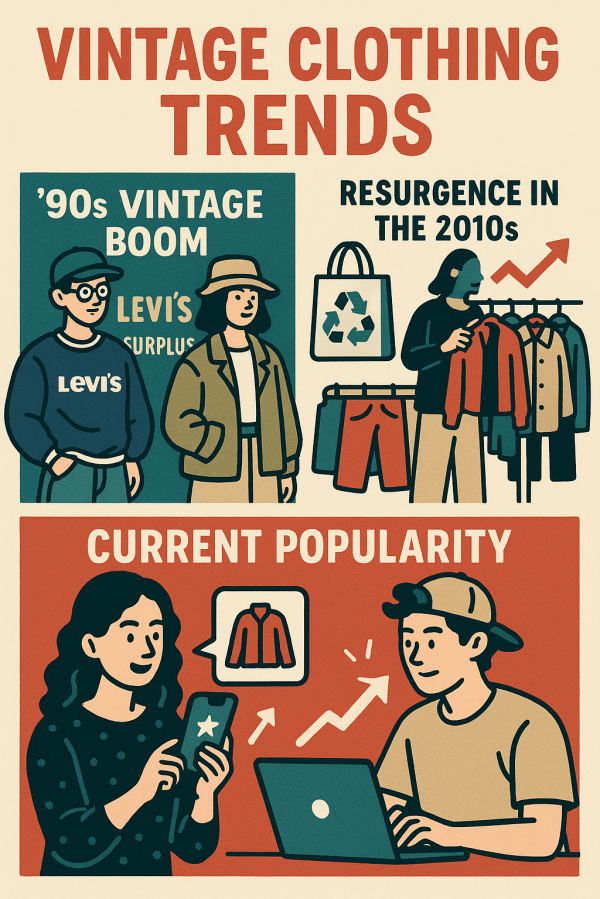最近、街中を歩いておりますと古着を扱うお店が増えたように感じます。
15年ほど前にもこんなブームがあったと記憶しています。
アパレル業界の消費動向は、時代ごとの社会背景や価値観の変化を映し出す鏡のような存在です。
その中でも面白いのは、古着ブームが繰り返し訪れていることです。単なる流行の循環にとどまらず、
世代ごとの消費意識やライフスタイルの変化がそこには色濃く反映されています。
90年代の古着ブーム
日本で最初に大きな古着ブームが起きたのは1990年代。アメリカ西海岸のストリートカルチャーや
原宿のファッションシーンと結びつき、リーバイスのデニムや軍物ジャケットといったヴィンテージアイテムが若者に熱狂的に支持されました。当時は「新品よりも古着のほうに価値がある」という逆転現象が起き、
独自のスタイルを求める若者の自己表現の手段として古着は広まりました。
2000年代以降の低迷と再燃
2000年代に入ると、ファストファッションの台頭により安価で流行を取り入れやすい服が市場を席巻しました。古着は一時的に下火となりますが、2010年代後半から再び注目され始めます。
その背景には「環境配慮」「サステナブル消費」という新しい価値観の浸透がありました。衣服廃棄問題や
大量生産の裏に潜む社会課題が可視化される中、古着は単なる“おしゃれ”ではなく“持続可能な選択肢”として
評価されるようになったのです。
Z世代がけん引する現在の古着人気
現在の古着ブームを支えているのはZ世代です。SNSでの発信力を活かし、古着をミックスした独自のスタイルを瞬時にシェアできる環境が整いました。トレンドの循環が早まるなか、「他人と被らない」「個性を出せる」
という古着の魅力は強みとなっています。また、フリマアプリやECサイトの普及によって、
古着を手軽に入手・販売できる仕組みが整ったことも消費行動を後押ししました。
繰り返すブームの本質
古着ブームが繰り返される背景には、単なる懐古趣味や価格の安さだけではなく、
消費者の価値観の変化があります。90年代は「個性」、2010年代以降は「環境配慮」、
そして現在は「デジタルとリアルをつなぐ新しい体験」として古着が選ばれています。
つまり古着は、時代ごとの課題や欲望を映し出しながら、形を変えて再評価され続けているのです。
アパレル市場全体の中での割合でも、古着市場は拡大を続けています。消費者が「ただ着る服」ではなく
「意味のある服」を求める限り、古着ブームは今後も新たな形で何度でも訪れるでしょう。
アパレル物流に強い佐志田倉庫の紹介
新しく開設しました埼玉県にあります上尾営業所では賃貸や業務委託の案件を引き続き募集しております。
その他エリア問わずニーズがございましたらお問い合せフォームやお電話にて
お気軽にお問い合せいただけますと幸甚です。 松﨑